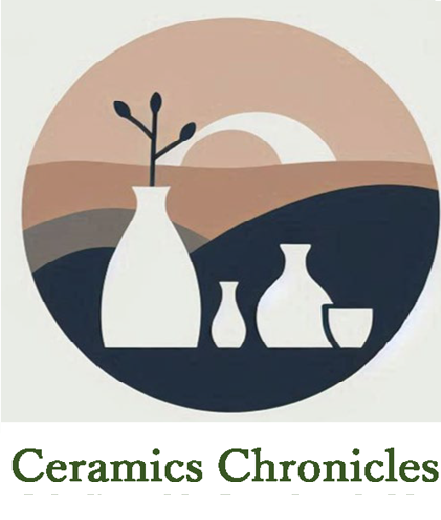やきもの紀行 (旧ぐい吞み旅)
その二十 高知県 安芸・高知 2001年
土佐 内原野・能茶山・尾戸焼





鳴門で一泊、いざ土佐へ出発。道中、初“徳島ラーメン”で腹ごなし、両県民に叱られそうですが、対岸“和歌山ラーメン”にどこか似たお味でした。現在、瀬戸内から土佐へは電車・車共に四国山脈を突っ切ってダイレクトに高知に向かうルートが一般的だと思います。この旅は四国一周旅です。徳島から海岸線をひた走ります。次の宿泊地室戸岬に向かう途中、サーファーに混ざって黙々と歩く同行二人お遍路さんの日焼けした姿が今も目に焼き付いています。室戸に近づくにつれ右手は切り立った巨大な岸壁、左手は茫洋たる海に一変します。空気も新鮮濃密になってゆきます。北は急峻な四国山脈に抱かれ、南は太平洋の大海原と対峙する土佐の風土を肌に感じる瞬間でした。室戸岬に差し掛かると突然巨大な武士の銅像が目に飛び込んできました。幕末の志士“中岡慎太郎像”です。桂浜の“坂本竜馬像”は有名ですが、こちらは聳え立ちド迫力で、この土佐入りお出迎えには脱帽でした。四国八十八箇所霊場第二十四番札所「最御崎寺(ほつみさきじ)」に旅の無事を祈願し、その夜は室戸岬の鄙びた宿をとりました。
翌日は、前情報が取れなかった安芸の“内原野焼”(*1)を探して、「内原野陶芸館」を訪れました。意外にもそこは陶芸教室主体の施設でした。内原野焼らしき資料展示も見当たらず、不徳にも戦意喪失、ろくな聞き取りもせずその場を去ってしまったのが大きな敗因でした。やきもの旅にはこのような苦い思い出もあります。
⦅実は、現在も窯元4件(原峰窯、福留窯、野村窯〈休業〉、陽和工房[2021年時点])が存在し、私が探索した場所より山手の弁天池周辺に点在しているとのことです。⦆
思い直して「安芸市立歴史民俗資料館」に手掛かりを求めて訪ねました。お目にかかった学芸員の方が何故か内原野焼の現状に不案内で申し訳なく思われ、同館で開催された特別展「土佐のやきもの」の資料を下さいました。尾戸、能茶山(のさやま)、内原野焼古陶の掲載写真からその実態を図り知ることが出来、とても参考となりました。
当館は安芸城址にあり、近隣には渋沢栄一のライバル“岩崎弥太郎生家”があり、また土用竹の生垣が美しい武家屋敷の並ぶ“土居廓中“を散策しながら、”野良時計”を望むのんびりとした空気感は格別のものでした。その日は桂浜で宿をとり、桂浜を眺望できる大浴場で旅の疲れを癒しました。
土佐2日目、朝快晴の桂浜で坂本竜馬像にご対面(そういえば亀山社中は長崎亀山焼とは縁が深かったのでは)。はりまや橋近くの食堂で本場“鰹のたたき”をいただき、いざ能茶山へ出発。この旅のハイライトの一つに土佐の尾戸焼(*2)、能茶山焼(*3)がありました。理由は、「森田久右衛門日記」と「久野正伯(くのしょうはく)」の存在でした。
前者は江戸初期仁清の時代に、江戸藩邸出府の往還約一年間、各地の窯場を訪れ、その詳細を記した貴重な記録です。後者は、藩窯開設のために招聘された大阪高津の陶工で、5年の滞在中に尾戸焼を興し、二人の弟子を残して帰阪した謎の人物です。江戸中期以降、木米、旦入、保全、道八、亀祐、長造、香山、清風与平、吉向治兵衛といった錚々たる京、大坂の名工が藩窯指導に招聘されることはありましたが、江戸初期に大坂より招聘され、長次郎、仁清風の洒脱な作風を伝え、肖像画まで残している陶工は極めて稀ではないでしょうか。
尾戸焼は、高知城北側尾戸(小津)より文政三年(1820年)、藩の殖産興業政策に従い能茶山に移されて以来、この地で茶陶と民陶の双方を焼き、今日に至っています。
というわけで、市街地より鏡川を渡った鴨部の地、能茶山(のさやま)「尾戸焼窯元」に土居庄次氏を訪ねました(土居窯の近くにはもう一軒、明治より続く谷信一郎氏の「谷製陶所」が今に続いています[2021年時点])。土居氏は、正に“いごっそう”らしいお人柄で応対してくださいました。庄次氏曰く、弟君は絵付け上手でしたが近年先立たれ、今は庄次氏のご子息が絵付け修行中とのこと。弟君の遺作は数少なく伝統柄“松竹梅”茶碗と“秋草の絵”茶碗くらいが残るのみとのこと。現代的で爽やかな“秋草の絵茶碗”をいただいて帰ることにしました。ぐい呑みについてお尋ねすると、奥様が「もっとよいものがあったのですが、今はこれしかないので」と上手を勧められず残念そうなご様子、すぐさま“ぐい呑み”とその“誠実さ”を頂戴しました。立ち去り際に、庄次氏ご夫妻が表まで見送ってくださったこと、今も良き思い出となっています。
【 メモ 】
(尾戸焼土居庄次造り 秋草ノ絵茶碗)
寸法(mm):長径128x 畳付き径55 x 高さ85(内高台8)
(能茶山焼酒盃)
寸法(mm):長径55x 畳付き径35 x 高さ43(内高台6)
(*1) 内原野焼:江戸時代安芸を治めた山内藩家老で安芸城主五藤主計が、当地の良質粘土に目をつけ、文政12年(1829)京都より陶工を招き福留芳右衛門等に学ばせたのが始まりのようです。藩に築窯の許可を願い出た記録(「内原野窯焼仕成願」など)が残っています。また、当初は酒徳利生産が中心でしたが、次第に灰釉、飴釉、緑釉、褐色釉主体の水瓶、すり鉢、片口、手水鉢、行平、おろし皿、湯たんぽなどの雑器生産が増え、大正末期から昭和初期にかけては窯元6軒、従事者50人以上と全盛期を迎え、京阪神への出荷も増加しました。
戦後は物資不足もあり、生活用品を中心に生産が追い付かない時期もありましたが、昭和30年~40年代は化学製品の普及もあり、主に土佐寒蘭などの鉢生産へ移行してゆきました。昭和40年から44年にかけて、安芸出身の現京都市立芸術大学初代学長・長崎太郎氏の呼びかけで、卒業生の陶芸家3名が内原野に入り、陽和工房を興し内原野陶芸館を拠点に新風を吹き込んでいます。現在、原峰窯、福留窯、野村窯〈休業〉、陽和工房4件(2021年時点)が、鉢物、伝統民芸品、花器、茶器などを生産しています。
(*2) 尾戸焼 :承応2年(1653)、二代藩主山内忠義が執政野中兼山に命じて、大坂高津の陶工久野正伯を招いて、高知城北側の尾戸(小津町)に窯を開いたのが始まりとされています。正伯は、森田久右衛門と山崎平内を弟子として指導にあたり、尾戸焼の基礎を築いて万治元年(1658)頃、後を託して帰阪します。初代森田久右衛門光久は13歳で正伯の最初の弟子となり、前述の「森田久右衛門日記」を残し、正徳5年(1715)に没します。その後、森田、山崎両家は明治維新まで七代続きます。文政3年(1820)、藩政により能茶山に磁器窯を開設するに至って、陶器方の縮小もあり、両家も尾戸より能茶山に移されますが、その後も陶器を焼き続けました。
明治になって、藩窯は民営となり、八代森田潤が尾戸焼復興につとめ、市原見山、西和田久三郎、土居栄作らが活躍します。大正、昭和にかけて、中島空哉、中西宗晋、川田蘭山、中川半九らが活躍。現在、土居窯と谷窯の二軒が尾戸焼の伝統を伝えています(2021年時点)。
(*3) 能茶山焼(のさやまやき):文政3年(1820)、藩財政は益々逼迫し、殖産興業による立て直し策として、能茶山に磁器窯を開きますが、土佐には磁器職人はおらず、伊予の砥部より肥前大村出身の樋口豊蔵を招き、次いで讃岐から市郎右衛門、更に砥部、平戸、筑前から職人7名を雇い入れます。苦心の末、11年後の天保2年(1831)に良質の製品を焼けるようになります。多くは、染付の皿鉢、花入、砧徳利、文房具、食器類で、稀に茶器や色絵もみられ、壬生水石や徳弘薫斎等の文人による絵付作品もあり、当時の好みを反映し珍重されたようです。明治初年に50余年の短い歴史を閉じます。
参考文献
「特別展 土佐のやきものー尾戸・能茶山と内原野」 安芸市立歴史民俗資料館刊行
「日本の藩窯(西日本編)」 彦根城博物館刊行
「伝統と歴史 土佐の焼物 内原野焼略譜」 野村製陶所栞
「内原野焼(土佐の手づくり工芸品)」 高知市公式ホームページ