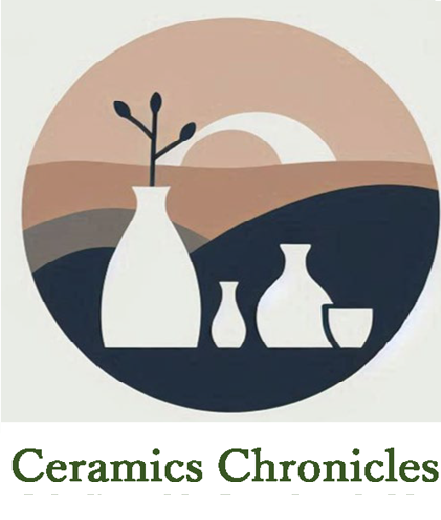やきもの紀行 (旧ぐい吞み旅)
その十七 沖縄 首里 2005年
謎のぐい呑み?








2005年、再び沖縄を再び訪れました。私の旅はほとんど家族旅行で、家内と同道の旅です。沖縄は伝統工芸の宝庫、家内のライフワーク“いとへん”の旅もないがしろにできません。読谷山花織(ゆんたんざはなうい)、大宜味村芭蕉布、首里織、紅型(びんがた)と工房を巡り歩きました。首里を散策中に紅型販売店を訪れた際、店内随所にディスプレイされた琉球工芸品の数々に目を奪われました。「謎のぐいのみ」との出会いでした。それは、これまで見て来た“やちむん”とまったく異なる姿かたちをしており、私はほとんど反射的に紅型店でディスプレイ用の「ぐいのみ」を譲ってくれないかという無謀な交渉を始めていました。店員さんも対応に苦慮され、オーナーと相談して後日連絡を下さることになりました。その日は沖縄最終日でしたので、帰郷後に電話連絡ということになりました。
店員さんの話ですと、店内のディスプレイ品は骨董商から買い求めたものとのことでした。
後日、譲ってくれるとの連絡があり、送金の後にはるばる我が家へやって来た次第です。
ひとつは、上焼(ジョーヤチ:施釉陶)で、もう一つは荒焼(アラヤチ:無釉陶)ですが、上焼のほうは現在では見かけない黒釉に上絵付の植物を描いており、見込みは灰釉単味で撫でてありますが、外面は“轆轤目”でも“削り目”でもなく、“ひも作り”の渦巻き状の凹凸を撫でず残しています。植物の絵付けも“白い花”と“青い葉”で見かけない素朴な構図です。畳付きは白く磁器化しています。
もう一つは、焼き締め(南蛮)の盃ですが、赤みを帯びた褐色で、厚さ1~2mmに薄く挽かれており、重さ32gと手取りも軽く、見込みに灰被りの跡が見られます。こんなに薄く小さいのに高台が丁寧に轆轤で削り出されています。磁器では見たことがありますが、焼き締めでは見たことのない薄造りです。陶工の技術とセンスの高さが伺われます。
長年、我が家で放置されていましたが、この風変わりな沖縄の焼物について、調べてみたくなりました。壼屋焼の起源は、1682年尚貞王の命により喜名、知花、涌田に分散していた窯場を新たに壼屋に統合したことにはじまります。壼屋以前には涌田(壷川)窯のほかに、北部名護近郊の古我知窯(*1)がありました。考古学調査によると「黒褐色を基調とし、灰釉に混じり黒釉陶も焼かれ、胎土は精製された白土が使用され、そのため焼成温度が高く、磁器質に近い焼となっている」とのこと。壼屋焼の源流涌田や古我知の窯において黒釉陶や青、白の絵付けが既に施されていたようです。戦前に民藝運動が沖縄に伝播し、その影響下で金城次郎氏ほか壼屋陶工により今日の意匠が形成される以前には、このような素朴な上焼が作られていたようです。
また、仲村渠致元(*1)は1724年王府の命により八重山に陶器造りの技術指導に赴いており、今日でも八重山の古墓から同様の陶器群が発掘されることから、広く琉球諸島内に流通していたようです。
もう一つの荒焼については、現在も由来が掴めず謎のままです。中国、韓国、薩摩経由の陶磁器も発掘されることから、琉球外のものかも知れません。また、意外と年代の浅い沖縄のものかも知れません。こんな小さな焼物ひとつから想像の旅は続いてゆきます。再び、沖縄や八重山を訪れたい思いがつのります。
【 メモ 】
(黒釉草花上絵ぐい吞み)
寸法(mm): 長径71 x 畳付き径26 x 高さ45 (内高台4)
(南蛮小平盃)
寸法(mm): 長径72 x 畳付き径25 x 高さ36 (内高台7)、重さ32g
(*1)古我知窯: 琉球陶祖平田典通(ひらたてんつう)と、弟子で中興の祖仲村渠致元(なかんだかりちげん)らは涌田窯で作陶するが、尚寧王の1617年に薩摩島津氏に懇願して、一六、安一官、安三官の三人の朝鮮人陶工を連れ帰り、涌田で陶技を指導させたが、古我知窯は涌田窯より遅く、平田典通に始まり、後に朝鮮陶工三人の試験窯であったとの見解がある。
参考文献
沖縄県立博物館紀要第14号、1988、「灰釉碗からみた近世沖縄古窯の編年」(知念勇、池田栄史、江藤和幸共著)
沖縄県立博物館紀要第17号、1991、「灰釉碗の話」(池田栄史、津波古 聡共著)