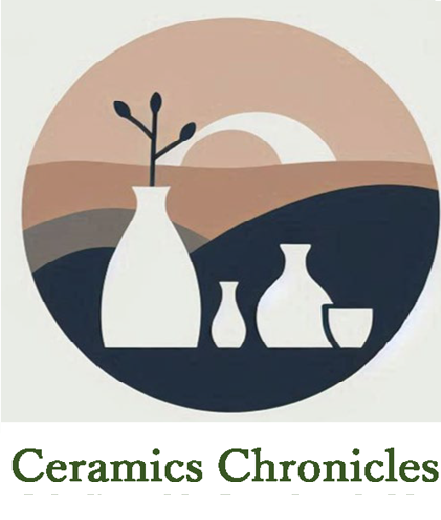やきもの紀行 (旧ぐい吞み旅)
その二十七 島根県松江市 1997年
布志名焼―多様なる選択(袖師・湯町・舩木窯)

















松江市街から宍道湖通りに沿って、天神川を渡った辺り、民藝運動の指導者達が訪れた頃もそうであった様に、いかにも職人さんの陶房といった風情の木造家屋に「袖師窯」さんを訪ねました。
職人さんが並んで轆轤に向かう陶房脇の展示室には多種多様な器種が並び、出西窯や湯町窯さんの洋食器が並ぶ雰囲気とは違って、懐かしい昭和・大正の和食器が並んでいました。また、これまで訪ねた民窯の日用雑器とは趣を異にして、和風な町の暮らしに溶け込む、工夫を凝らした粋なデザインの陶器たちでした。この地の主な民藝系窯元が戦後に旗揚げしたのに対し、袖師窯さんは昭和6年と早い時期に運動に参加された経緯と小泉八雲の愛した松江市街に近い立地条件が影響しているのでしょうか。
酒器と見まがう青とグレーの煎茶碗2種をぐい呑みに見立てて持ち帰りました。
次に向かったのは、山陰の名湯“玉造温泉駅”近くの「湯町窯」福間秀士氏でした。和風建築ながら、どこか南欧を思わせる明るい店内には民藝を代表するスリップウェアの器が整然と並んでいました。求めていた布志名焼の「来待釉」の黄色と飴釉、そして福間氏のお人柄が店内を明るくしているのだと気づきました。
バーナード・リーチと濱田庄司によって、日本に紹介されたスリップウェアを主体とする陶器の収集は、英国コーンウォール地方最南端の港町セント・アイヴス周辺で焼かれていた伝統的な民陶から始まっています。スリップウェア技法は元来、古代中国、古代中東に始まり、アフリカ、アメリカ大陸、初期朝鮮、古代ギリシャ、イスラム文化圏と世界中で行われており、17~18世紀英国で盛んに使われた技法でした。英国でも比較的温暖なこの地は避暑地としても親しまれ、古代ローマの円形劇場跡を残す土地柄です。明るい色調と文様はコーンウォールの風土からもたらされたのかも知れません。
布志名焼湯町窯さんは、作家を名乗らず、民藝運動の精神を忠実に体現しつつ、三代にわたってリーチの伝えたスリップウェアを自家薬籠中のものとして、今日の生活を飾る実用の器を作り続けておられる代表選手ではないでしょうか。
湯町窯さんの“元祖エッグベーカー”と来待釉と白釉を掛け分けたぐい呑みをいただいて帰りました。
次に向かったのは、宍道湖畔の「元祖布志名焼舩木窯」さんでした。前回ご紹介した土屋善四郎の興した雲善窯とは目と鼻の先です(布志名焼発祥にまつわる歴史的な背景を感じさせます)。宍道湖を眺める絶景のロケーションに瀟洒な陶房兼ご自宅を構えておられました。舩木研児氏と奥様が迎えてくださいました。リーチが逗留し、多々納氏、福間氏等民藝運動に賛同する若き陶工がリーチの指導を受けるべく参集した舩木道忠氏のお宅です。
伺った当時、研児氏はお体が不自由なご様子で、奥様が介助で同伴されていました。小生ごとき輩をご不自由な体を押して迎えて下さり、終始対応してくださいました。体調のためか、洋風な小間に作品の数も少なく、陶板にスリップで動物が描かれた小品や鉄釉のカップが展示されていました。特に、鉄釉カップからは、民藝から出発し、現代陶芸の領域に踏み込まれた氏の布志名の土と釉薬へのこだわり、器に表現された現代アートに通じるテクスチャーの存在感が時代を超えて語りかけてくるように感じました。
今回、この鉄釉が布志名焼を代表する来待釉ではないかと気づきました。来待釉は黄色一辺倒ではなく、鉄分系との化学反応で焼成温度により黄色、茶褐色、赤褐色に変化する釉であることに気づきました。
私は、スリップウェアの方ではなく、カップの方を選びました。帰りを玄関の外まで奥様と見送っていただき、一緒に記念写真まで撮らせていただきました。今も温かく、良き思い出として心に刻みついています。
今回、もうお二方を紹介させていただきます。舩木研児さんの二人のお弟子さんです。お一人は島根県雲南市三刀屋で永見窯を興された永見克久氏。もうお一方は出雲地方に根差した現代陶芸家三原研氏です。このお二方は、舩木研児氏が内包されていた異なる方向性をそれぞれに歩まれました。
永見氏は出雲の山間の地三刀屋で、民藝に根差した健やかなオリーブ色の食器を焼いておられます。シンプルでありながら温かく、不易流行のデザイン性を持った焼物です。後年、倉敷民芸館で独り出店されたいたところ偶然にお会いして以来、いつも気になっていた陶工です。朝食はオリーブ色のトーストやサラダ皿として、今も食卓を彩ってくれています。酒器は見当たらず、今回ご紹介できませんでが、こころある民藝店で食器を入手されんことを願っています。
三原研氏は、古代出雲地方の祭器や神話を想起させる独特のフォルムとテクスチャーが放つ存在感で、現代陶芸界異色の作家です。
共に舩木研児氏に師事されましたが、私には師の民藝的側面とそれを越えた現代陶芸的側面をお二方が継承されているように思えて今回ご紹介しました。
石見・出雲地方の焼物旅はこれにてお終いです。夏季休暇タイムリミットで因幡・伯耆はいつの日にかまたという次第です。
この旅の記憶を通じて、侘び寂びの茶陶(萩焼・出雲焼)、赤い石州瓦、日用雑器の石見焼、民藝の出西焼・布志名焼、そして現代陶芸作家を垣間見て来ました。対岸は中国大陸・朝鮮半島、古代より玉を造り、たたら製鉄を行ない、世界を揺るがした石見の銀を産出し、海運を使って広く交易を行なうなど、多様な最新技術が行き交ったこの地方の焼物という最新技術も、誠に多様な発展を遂げてきたことを痛感しました。不易流行の精神をもって、21世紀をどのように逆転の発想で乗り越えてゆくのか、砂丘の砂の一粒でしかない微力な私ですが、何かお役に立ちたいと願うばかりです。
【 メモ 】
(袖師窯)
・糠白釉笹絵文茶器
寸法(mm):口径75x 高台径36 x 高さ48(内高台10)
・呉須地掻き落とし文茶器
寸法(mm):口径80x 高台径37 x 高さ51(内高台10)
(湯町窯)
・ぐい呑み
寸法(mm):口径60x 底径34 x 高さ54(内高台7)
(舩木窯)
・ 舩木研児作 布志名釉カップ
寸法(mm):口径72x 底径50 x 高さ60(内高台15)
(三原研)
・ 炻器盃
寸法(mm):口径55x 底径50 x 高さ66(内高台0)
〇布志名焼と舩木窯
・元禄の頃(1695年頃)「舩木与次兵衛村政」が布志名に移り住み延享元年(1744)の隠居をきっかけに、3人の子が各々窯元を興す。現在の舩木窯がその始まりとなる。
・その後(1780)、松江藩の藩命により、楽山窯より元祖「土屋善四郎芳方」が布志名に移住して指導に当たり、多くの優品を残す。
・松平不昧の指導を受けた土屋、永原の藩窯と舩木系子孫らの民窯が併存する。藩御用窯と日用雑器を北前船で出荷する民窯の棲み分けが行われる。
・明治に全盛期を迎え、布志名焼特有の黄釉色絵陶器は、海外にも販路を拡大する。
・昭和に入り、元祖布志名焼舩木窯「舩木道忠」氏の時、柳宗悦、河井寛次郎、濱田庄司、バーナード・リーチ等の民藝運動の影響により、スリップウェアの技法が当地に移植され、独自の工夫改良努力により、民窯の洋食器製作普及を促進する。
・道忠氏のご子息舩木研児氏(1927-2015)は、1950年(昭和25)濱田庄司に師事し、数々の賞歴を重ねた後、1967年(昭和42)に渡英。セント・アイブスのリーチ氏と子息デビッド氏の下で指導を受ける。帰国後も民藝の域を超えた現代的な作品製作で活躍される。吹きガラス作家舩木倭帆(ふなきしずほ)氏は研児氏の弟君。
・現在、舩木窯は研児氏のご子息伸児氏により、現代感覚を持った今日のスリップウェアをはじめとする作品で活躍中。
〇スリップウェア
「スリップウェア」のスリップとは、粘土や鉱石の調合で作られる「化粧土」のこと(文字通り、地釉や化粧土の上に化粧土を滑らせる意)。先ず、生乾きの器面全体に地色となるスリップを掛ける(湯町窯の場合、弁柄)。その上からスポイトでスリップを細く垂らしたり、筆や指で描いたり、更にそれを櫛状の道具で引っかいたりして文様を描く、日本の「筒描き(イッチン盛り)」と同様の技法である。また、全体にかける地色のスリップは陶土の粗い素地をコーティングし、滑らかで美しい表面に仕上げる効果も兼ねている。古来の一回焼では1,000度前後、近年の二回焼(下地、上描き)では1,300度前後の焼成となる。
バーナード・リーチや富本憲吉は1913年、東京丸善書店で入手したチャールズ・ロマックス著「古風な英国陶器」の中で、初めてスリップウェアを知る。リーチの英国一時帰国に同行した濱田庄司は、セント・アイブスの彼らの窯近くでスリップウェアの陶片を見つけ、現存品の収集し、1924年濱田が日本に持ち帰る。これを眼にした柳宗悦や河井寛次郎も加わり、スリップウェアはその後の民藝デザインに大きな影響を与える。
〇来待釉
来待釉の素となる「来待石」は、宍道湖南岸で採掘される「凝灰質砂岩」の事。古代には石室、石棺に使用、中世には供養塔、墓石、石段、石垣などに使用される。江戸時代には松江藩外への持ち出し禁止となる。江戸後期になると、「出雲石灯篭」や狛犬(「出雲唐獅子」)として全国へ運ばれた。“石粉を利用した石見瓦や石見焼の釉薬原料としても活用される”。鉄分の多い石見などの陶土や下掛けした弁柄(酸化第二鉄)などとの化学反応により黄色を呈し、1300度以上の焼成で石見瓦の赤褐色を呈する。耐熱・耐水・耐酸性に優れている。
〇袖師窯
宍道湖の干拓が進む以前は袖師ケ浦の湖岸に位置する窯場であった。1877年(明治10)、布志名や楽山で修行を積んだ尾野友市氏によって松江市上乃木皇子坂に開窯。二代目尾野岩次郎の時、宍道湖岸の景勝地であった袖師ケ浦に窯場を移し、5室の登り窯を築いた。三代目尾野敏郎氏は昭和6年より柳宗悦、河井寛次郎、濱田庄司、バーナード・リーチ等の指導を受け「暮らしに役立つ健やかなやきもの」を目指す。父の遺志を受け継いだ4代目尾野晋也氏(2012年他界)によって、地元の土を使い、地釉、柿釉、辰砂、藁白釉、糠白釉、呉須などを使って、掛分、抜蝋文、鉄絵、刷毛目、釘彫、櫛目などの技法を駆使し、素朴さの中にも温かく洒脱な絵付け・文様の日用の器を造り続けている。1958年のブリュッセル万国博覧会で「掛分酒器」がグランプリを受賞。現在は五代目尾野友彦氏が継承されている。
〇湯町窯
1922年(大正11)開窯、主に火鉢を産す。1935年(昭和28)、布志名焼を訪れたバーナード・リーチは舩木窯舩木道忠氏宅に逗留し、ピッチャーの作り方、ハンドルの付け方、スリップウエアの技法などを指導する。その間に布志名焼湯町窯2代目福間貴士さんや出西窯の多々納弘光さん達も合流して指導を受ける。土質と釉薬、低火度での焼成など本国英国と似通った条件の布志名焼が取り組みやすかったのだろう。一連の指導の成果もあって、出西窯、湯町窯、舩木窯共に洋食器を主体とした製品を展開する。リーチの来訪時に “元祖エッグベーカー”は湯町窯で製作が始まった。この地で採掘される来待石を原料とする、この地独特の“来待釉”という黄釉を使ったもの、黄釉の代わりに藁灰釉を掛けた青白い海鼠釉の製品がある。リーチ直伝のスリップウェアやハンドル付けなどの熟練の技が今も健在で製品の骨格をなしている。パンフレット、栞などのイラストを、民藝運動を通じてこの地に縁の深かった棟方志功氏が描いているのも民藝の情趣を誘う。3代福間秀士氏と4代庸介氏で今日に続く。
参考文献
「民藝の教科書① うつわ」久野恵一監修 荻原健太郎著 グラフィック社 2012年4月
「袖師焼」栞
「湯町窯」栞
「布志名焼舩木窯」栞
「モニュメント・ミュージアム 来待ストーン」ホームページ
「Wikipedia」